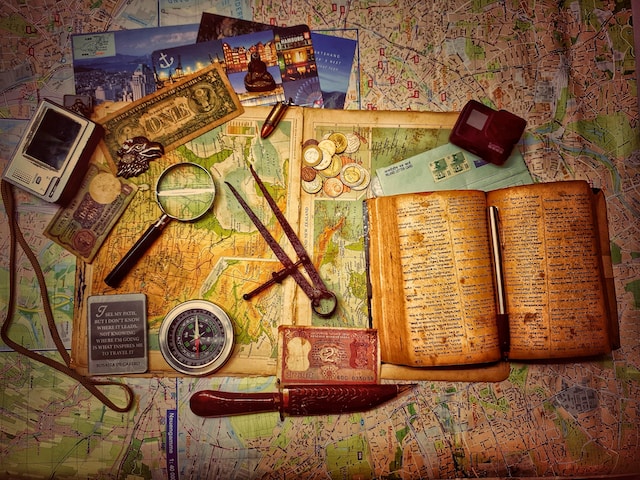どうも、メケです。
ユヴァル・ノア・ハラリ著書のサピエンス全史です。
前記事では近代以降、社会秩序安定のために使われていた宗教に変わってイデオロギーが台頭してきた。そして科学革命には帝国とこのイデオロギー「資本主義」が資金ポンプになって科学革命を後押ししてきた。といった内容でした。
強欲にかられた資本主義者たちは留まるところを知らず、無関心が産んだ悲劇、大西洋奴隷貿易では大量の犠牲者を出した。他にも工場労働者やコンゴ盆地のプランテーションなどでも大量の犠牲者を出した。
しかしながら資本主義によって教授できている部分もあるし、今更資本主義以前の社会には戻れない。資本主義をいくしかないなぁといったお話でした。
経済成長には大量のエネルギーと資源が必要だった。ある時点で発想の転換点が起こった。どんなエネルギーも機関と機械を使えば必要なエネルギーを転換できると。すなわちエネルギーは無限に増やせるという発想。それが産業革命。
イギリスで起こった産業革命からはじまって、今やエネルギーは無限大。
原子力発電所、エンジン、電灯、そして太陽エネルギー。科学革命はすべてエネルギーを変換する革命であった。
目次
エネルギー転換の発想と原材料の発見、発明によって産業革命がおこった
どこでそういうエネルギー転換の発想に切り替わったか。
それはイギリスの炭鉱での話
人口増加によって薪不足のため石炭を燃料としていたのだが、地層深いところの石炭は大量の地下水も出てくる。この地下水が悩みだった。そこで石炭を燃料に水を沸騰させその蒸気でタービンを回転させポンプに力を伝え水をくみ上げることを思いついたのだ。
このポンプ(機関)が炭鉱を出て織機、紡績機などに転用された。それから蒸気機関車、エンジンなどの内燃機関。エネルギー転換の発想によって一度に輸送できる原料や人が爆発的に増えた。
機関、機械の開発、原材料の発明
プラスチックを発明したり、火薬の原料であるアンモニウムを空気から作れるようにしたり、シリコンやアルミニウムを発見。アンモニウムを安価に製造する技術を開発したり。
こういったことで生産品のコストは大幅に安くなり産業がどんどん発展していった。
結局のところエネルギーをほかのモノに変換できるということと、新しい材料の発見と安価に製造できる方法の発明のおかげ。
→いやまさにこれはすごいこと。これによっていろんなエネルギーを自分たちの欲しいエネルギーに転換する機械さえ作ってしまえばいい。エネルギーは無限に手に入るようになったということ。
家族とコミュニティの崩壊
昔は家族とコミュニティ中心に回っていたけど、今は個人の時代。ある程度のお金さえあれば生きていけるし、病気になれば病院がある。自活できなければ生活保護もある。老後は老人ホームがあるし、介護だってしてもらえる。結婚したけりゃ結婚紹介所だってある。こういったものを昔は全部家族や近所のコミュニティがやってくれていた。今は国家の力が大きくなって全て国やソーシャルワーカーたちがっやってくれる時代なのだ。
→田舎じゃ決してそんなことはないと言いたい。まだまだ家族やコミュニティは健在だぜ。
だから? だから何? いや、今めっちゃ平和っしょ!
今はめっちゃ平和な時代だとハラリは言っている。
ハラリは核兵器を開発したことが、逆に平和につながっているのだと述べている。
→ここんところ私的には十分 「?」 はつく。
なぜなら、この本が書かれたのはまだウクライナとロシアの戦争が始まる前だったからね。
今はそうでもないよ。戦争によって穀物の出荷量は減り、ヨーロッパへの天然ガスや石油などの資源送油ストップ。それによって物価高になっているし。コロナ騒動のこともあるし。
戦争は起こっている。でも核兵器は使ってないけどね。
現代はカメレオン
ハラリはこうも言っている、現代はどんな時代か一言では言い表せれない。一言でいうなればカメレオン。
→だろうね。その時その時で時代はめまぐるしく変わっているからね。
文明は人間を幸福にしたか

ハラリの書いたこのサピエンス全史、歴史だけじゃない、人の幸福についても考えている。
→幸せを感じるためには幸せのハードルを下げた方がいい。そのことは自分も思っていた。あまり期待しすぎない方がいい。目の前の幸せに幸せと感じられるような生活にするのがいいって、実は常々思っている。
→そういった僕と同じようなことが結論としては書かれていた。
そもそも幸福にはある程度お金が必要。でもそれ以上はいらない。
幸福に家族は必要か?昔は家族やコミュニティは幸福度に影響していたが今は違うといっている。国家やソーシャルワーカーが面倒見てくれるから、らしい。
過去200年において物質的には劇的に状況が改善されたが、家族とコミュニティは崩壊したので、幸福度合いは相殺されたとハラリは言っている。
→ぼくはそうは思わないけど。田舎だからかな。
幸せ度合いは期待によって変わるとハラリは言っている。期待によるところが大きので、必要以上に期待させるマスメディアは我々の日常とのギャップの大きさに幸福感を枯渇させつつあるとも言っている。
→まさにそう。テレビで楽園のようなリア充を見せられると、どうしてもこちら側はそのギャップに気分落ちこむよ。インスタやTwitterもみんなのリア充見ちゃったら、「なんだかいいなー、それに比べて僕なんて」って、僕はそう思っちゃうな。下手にテレビとかメディア関連は見ない方が幸せだよ。
幸せに遺伝的特質が影響している=心の空調システム
最近の研究によって、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンなどの体内に生じる快感物質に、幸せが左右されることが分かった。
これらは体内で比較的安定しているようにプログラムされているらしい。遺伝は両親から受け継がれる。人によってプログラムされた幸福の度合いは生まれつき、その振れ幅は決まっているらしい。
心の空調システム
レベル5の人はレベル5の人なりの範囲内を上下。
レベル8の人はそれなりの範囲内で上下する。
つまりレベル8の人は無一文になろうとも、両手足を切断しなければならないような事故にあおうとも、最終的にレベル8ぐらいの心の空調システムは落ち着く。生まれつきレベル8の人は、何があろうと最終的にそれなりに幸せだということ。
一方レベル5の人はレベル8の人が幸せに感じるような日常のできごとでもレベル5のまま、大した幸福感は得られないままなのだそうな。
この心の空調システムは生化学システムの中に組み込まれていることが科学的に判明したのだそうな。
→へーな話である。つまりは結婚したら幸せになるのか?いやいやもともと、独身時代からそんなに幸せを感じないレベル5の人は結婚しても、最終的にはレベル5付近に落ち着くのだそうな。
→もしそうだとしたら、それはひどい話だよな。あなたは多幸感の少ない遺伝子を持っているから、結婚するなら多幸感の多い人と結婚したいわ。なんてえり好みされたりするんじゃないのか?
→一つの現象に対して「どこを見るか」「どのように反応するか」は癖ではなく、空調システムの範囲内でしか幸せ度は動かないというのか。遺伝なの?
→この本ではないですがセロトニンの原料となるトリプトファンを生成する食べ物もあるそうですよ。バナナとか。だから、遺伝なのだからと諦める必要もないとは思います。私的には。
サピエンスは私たちを幸福にしてきたか
幸福については最近科学者たちが研究を始めたばかりなので、適切な問いは投げかけても、議論に終止符を打つようなことはしたくないと、ハラリは言及を避けています。
→今までサピエンス全史読んできて「幸福」を私なりに解釈しますと、これだけ人類が地球上で繫栄して科学技術の恩恵を受けようとも、それによって幸せかどうかは一概には判断がつかないと思う。個人によるところが大きいのではないでしょうか。にしても戦争や争いの真っただ中を生きていた人々に比べれば客観的に見て幸せとは思う。てもそれ以外の場面では個人によるところが大きいのではないかなと思います。
これからホモサピエンスはどこへ向かっていくのか=超ホモサピエンスの時代へ
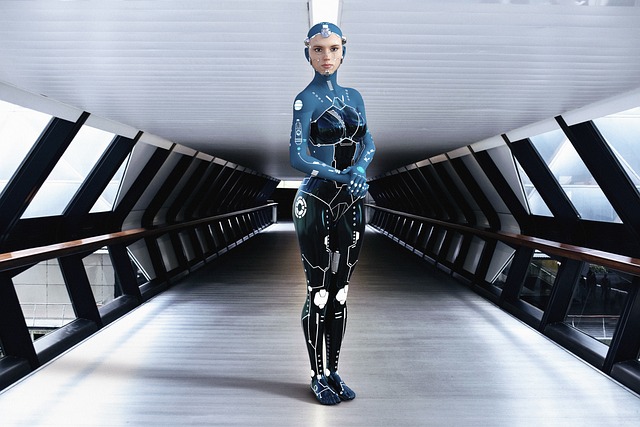
こんなところまでもハラリは述べています。
サピエンスの将来ですね。
早い話が、サピエンスでなくなってしまうのではないかと。
科学技術のおかげで遺伝子のゲノム解析まで実施した。ネアンデルタール人の毛髪の遺伝情報をもとにネアンデルタール人を復活させることもできるそうです。永久度凍土から発掘したマンモスだって復元できるそうです。技術的には。
人の耳のようなものをマウスの背中に培養した実績もあります。
目の見えない人が見えるようになったり。
腕を失った人が脳波を読み取って腕が意志通り動いたり、実際にそれに近いモノはでき上がりつつあるとのことです。
ゆくゆくは脳内とコンピュータをリンクさせてビッグデータに人間の脳がアクセスできるようにすることも近い将来は夢ではなくなるそうです。
ここまでくると、「サピエンス」とはどこまでのこと言うのか。
そしてAIが自己複製しだした時、人類では止めようのない世界になってしまうのではないかともハラリはいってます。
→どちらにしても50歳代の私が生きているうちに実現しそうにはないかもしれませんが・・・・。
今や科学技術はそういうところまで来ているそうです。
科学革命を超えた革命
しまいには自分たちの意識やアイデンティティまで科学技術でコントロールするようになるのではないか、ともハラリは言っています。
とすれば、私たちは何になりたいのか、といった疑問を最後にこの本を締めくくっています。
いやもしかしたら、この疑問は「私たちは何を望みたいのか」かもしれないと、ハラリは頭を抱えていました。
→ハラリは歴史学者であり、哲学者ですね。
まとめ
というわけでサピエンス全史、上下巻のレビュー終了いたします。
ホモサピエンスは認知革命、農業革命、科学革命の3つの革命によって躍進してきたと、そういった内容でした。
すべてを通して社会秩序を維持するために「虚構」を使って歩んできた歴史でもあったように感じました。
つまりは一番最初の認知革命で「虚構を語る力を手に入れたこと」がサピエンスにとって最も革命的できごとだったのではないでしょうか。
そう考えるとこのサピエンス全史は「認知革命」のところが一番面白かったかなと、私は思います。他の動物とは違い遺伝子による肉体的変化を待たずして、虚構を語る能力という突然変異だけで地球上のあらゆるところにまで進出してきたところはホントにすごい革命だと読んでて思いました。
次におもしろかったのはやはり科学革命のところです。
中世から近代に切り替わる付近から現代までです。宗教が影を潜めイデオロギーが台頭してくるところまで。
帝国と科学テクノロジー、この2つに資金という油をポンプのように送り続けた資本主義。そしてこの資本主義という虚構に「夢物語」を見させ続けてきてくれた「科学技術者たちの発見、開発の数々」。「同時進行した産業革命」によって得られる燃料や資源は無限大になった。おそらく直近500年は本当に目まぐるしく社会が変化してきた時代。この本読んでてこの「科学革命」もおもしろかったです。
そして何よりこの科学革命を下支えしたのが農業革命のときの「1,2,3,4,5などの書記体系」と貨幣通貨の発明。これが世界で同時多発的に生まれたのも驚きました。
科学革命の話に戻ります。
3年もかかった人類の遺伝子ゲノム解析。今では数日もあれば解析できるらしい。
そしてお金と倫理さえ許せばマンモスやネアンデルタール人も再び蘇らせる技術を持っているとのこと。そして意のままに操れる義手や義足、はたまたビッグデータと直に繋がった脳など、科学技術の可能性は広がります。
ココまで来るともはやこれをサピエンスと呼んでいいのか。ハラリのいう科学革命を超えた革命が起きようとしていると。。。
おもしろかったです。
本当に人類はどこへ行こうとしているのか。寿命が200歳ぐらいまで伸びるならその行く末を見てみたいものです。
最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。
長くボリューミーな壮大な物語でした。
それでは。