
どうも、メケです。
アンディシュハンセンさんの書籍で「運動脳」は有名ですが、それ以上に「スマホ脳」は有名なようです。
世のほとんどの方がスマホ、使いすぎは良くないと感じてるんじゃないでしょうか。
私もその一人。やり始めるとなかなかやめられないですから。
スマホは脳を虜にするようなメカニズムが絶対働いてるはずです。
目次
読む前の印象
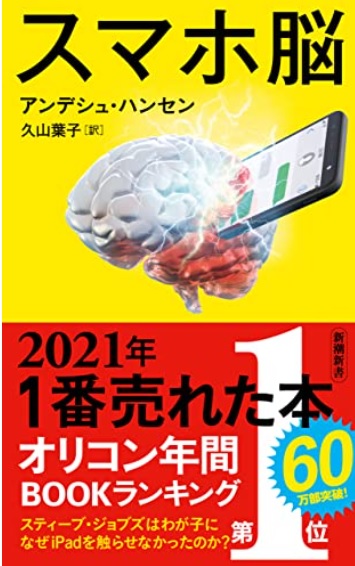
スマホ脳というタイトルから、スマホをしすぎると依存になるよという警鐘じゃないかなと思っていました。
一時期スマホが手放せないぐらいの頻度でほぼ一日中使っていました。今は一日に何回かしか「X」は覗きませんし、時間も少しです。
マジでハマったらなーんもできなくなる。いや、用事や運動、睡眠、休息、家族との時間など全くできなくなりますから。
私個人の体感として、スマホ使い過ぎはメンタルは落ちます。
この本を読んだのは「ハマりすぎる」裏付け(メカニズムなど)が知りたかったのもあります。
実際読んでみてどうだったか
スマホにハマるメカニズム書かれてました。そしてなぜ「うつ」になるのかも。だいたい僕の予想と当たってました。
しかし予想を裏切られた部分もあります。
実は警戒すべきは「スマホ」だけじゃなかったのです。
その他の「YOUTUBE、アマプア、Kindle」などのスクリーン電子機器全般に要注意だそうです。
こういったものに関わる時間すべてを「スクリーンタイム」というのだそうです。
私、スマホ時間は短いですが、「スクリーンタイム」長いです。
ブログ書くのに長時間PC使います。
好きな動画なんかは一日中、YOUTUBEやアマプラを見たりしています。だっておもしろいんだもん。そもそもが私、ハマりやすい人です。
Kindleだって好きな本は一日中タブレットで読書してます。
これら電子機器でスクリーンを見ている時間もスマホ同様に警戒が必要だそうです。
これらは「スマホ脳」にならないために警戒スべきアイテムたちだったのです。
「スクリーンタイム」、覚えときましょう。
ネットサーフィンや、動画視聴も程々にしたほうが良さそうです。
私、鑑賞するときは経過時間に気づけるように「タイマー」してます。
過集中な人、「スクリーンタイム」要注意です。
スマホ脳、ざっくりこんなコトが書かれていた
人の脳はデジタル社会に未だ適応していないということ。だから、スマホやiPadなどの使い過ぎは当然、人の脳や身体の様々な箇所に弊害がでてくる。でてきて当然。
そういう前提で考えた時、じゃぁ、スマホとはどういった使い方をすれば良いのかまで示してくれている指南書のようなもの。
そしてなぜ人類がここ数十年で始まったデジタル社会の波に飲まれて、精神的不安や体調不良を起こすようになったのか。
人の進化の観点からもわかりやすく説明してくれています。結構納得する内容でした。
スマホを含めた現代のデジタル社会は今の「人」に合っていない
スマホの使い過ぎによるストレスや、依存(ハマる)やうつは、今までの人の進化の観点から観ると至極当たり前の反応らしいです。
数十万年前の太古より生き延びてきた人類が、様々な脅威から逃れるために適応してきた結果であると。
人の脳や身体は今でも狩猟採集時代のままであると。人々が現代のデジタル社会に合っていないから様々な体の不調が起こるのだと。
体の不調はすべて身体の正常反応らしいですよ。
そもそも人はネガティブめであり、神経質であり、常に周囲の状況に気を配り、自分を取り巻く人達と自分の関係を気にするのに長けていた。そういった人たちがここまで生き延びてきた。
生き延びるために食料をもとめて常に動き回り、高カロリーな食べものを見つければ即座にすべて平らげる。そして飢餓に備えてできるだけカロリーを蓄える。危険には即座に反応して戦うか、逃げるか瞬時に行動を起こせるようにしている。脳内の自動警報装置が常に「ON」状態なのだそうな。
現代ではスマホ以外にも様々なストレスがたくさんあり、常にストレスにさらされています。
この本を読めば「スマホにハマったり、うつになるのはそりゃ仕方ないなぁ」と思えます。
スマホは現代の生活にはなくてはならないもの。スマホを全く使わないわけにはいきません。
なので、スマホを使いすぎると体調が悪くなるし、スマホ依存にもなるし「うつ」にもなるんです。そういう前提で「どのようにスマホと付き合っていけばいいか」までしっかりと自分に落とし込みたくなるような本です。
スマホを使いすぎると「うつ」になるのか→ほぼ、なる

スマホだけでなく、その他の「スクリーンタイム」が長ければ「うつ」になる、、、可能性が高いそうな。
ただ、みんながみんな「うつ」になるほど使いすぎるのかというとそうでもないようです。
ハマりやすい人とそうでない人がいるようです。
ハマりやすい人は「自尊心が低いが競争心は強く、自分を強いストレスにさらしている人たち」。
「怒りっぽく攻撃的、積極性に冨み活動的な人」。
「精神的にもろい人」など。
そうでない人は「おっとりしていて落ち着いた人生観の人」、らしいですよ。
というようなことが実験でわかっているとのこと。
スマホにハマる、メカニズム
狩猟採集時代より生き延びるために周囲の情報を得ることが重要だったから。
食べたい、学びたい、知りたい、未知の新しい体験をしたい。
これらは生き延びるために脳の報酬系が勝手に働く。
これらは性欲、食欲、睡眠欲と同様に人が進化の過程で得た本能。
やりたいことに集中するとドーパミン放出。
満足するとエンドルフィン放出。
快感。
スマホ→ドーパミン増加→脳の報酬系システムをハッキングされる→アプリメーカーの思うつぼ→スマホにハマる。
そういうメカニズムだったのですよ。
なぜハマるのか

人の噂話などのゴシップネタが好きだから
他人の悪い噂が好き。
他人が何をしているか、どんな関係にあるか、本能として知りたい。
人は自分のことを話している時、脳の報酬系が最も活発になるから
スマホは人間の報酬系を活発&注目させるための、とてつもない力を持っている。
いや、アプリは人々の脳をいかにすればハッキングできるか、計算し尽くされて開発されてきた。
SNSの「いいねやリプライ」、フェイスブックなどで「自分のことを語る時」、報酬系のドーパミンが放出される。
人類の進化学的に考えるとどうなのか→ハマるのはごく自然なこと
人は太古の昔より群れの中で相互扶助しながらでしか生きられなかった。
群れから追い出されると、それはつまり死を意味する。
ゴシップネタ大好き
群れの中のあの人は危険な人なのか、あの人とあの人は仲良しなのか、仲が悪いのかなど、自分が仲間はずれにされずに、群れの中で生き抜くためには重要な情報だった。
だから人のゴシップネタ大好き、噂話大好き、人の不幸話が大好き。
これはもう本能。
じぶん語り大好き
自分のことを語ると周りの人と絆を強め、周りが自分をどう思っているか知るためのいい機会になる。自分の発言に対する他者の反応を見ることで自分の行動を改善することができる。だから人は「自分のことを語る」と報酬系が活発になるように進化してきた。
これも本能。
そんな情報がスマホで簡単に手に入る。
ドーパミン、エンドルフィン出まくりで「もっともっと」となる。
スマホ使いすぎればそりゃハマるでしょう!
スマホは依存アイテムなのですよ。
スマホを使いすぎると、なぜ「うつ」になるのか

スマホなどスクリーン機器の長時間使用で生活に必要な時間を奪われるから
例えば食事の時間、風呂の時間、睡眠の時間、家族の時間、人と合う時間、運動する時間。
特に睡眠と運動が減ると「脳の機能」が低下しやすくなるそうな。
これはねぇ、以前読んだ「運動脳」という本にも書かれていた。
脳は運動が好き。逆に言うと、脳はじっとするのが嫌い。
スマホは脳の報酬系をくすぐる反面、脳が嫌いな「座り続ける」ということをしている。
そして運動をする時間がないから、運動による様々なホルモンの恩恵を受けられなくなる。
脳みその老化が進む。前頭葉が萎縮したり海馬が小さくなったり。
そのことにより、記憶力が落ちたり、集中力が落ちたり、学習能力が落ちたり。様々な弊害が起こる。
運動しないから睡眠にも悪影響が出る。
スマホの使い過ぎと合わせて運動しないから二重に寝られなくなるわけだ。
スマホの使い過ぎで運動や睡眠時間の確保ができなる弊害はかなり大きいようだ。
夜遅くのスマホで睡眠障害が起きるから
スマホのブルーライトが入眠を遅らせて睡眠を妨げている。
メラトニンが低減し、身体を目覚めさせる。
スマホだけじゃない。他のパソコン、キンドルなどのモニターからもブルーライトは出ている。
脳や身体が長期間ストレスにさらされるから
ブルーライトによってストレスホルモンのコルチゾールやグレリンが増加することがわかっている。
グレリンは食欲を増進させるホルモン。
コルチゾール増加によってPHA系が発動する。
PHA系とは視床下部→下垂体→副腎までの間でストレス(コルチゾール放出)の発動するまでのメカニズムのこと。
身の回りの危険に即座に反応するための「脳内の自動警報システム」。
本来は警報は発動しても3分ほどで解除される。
狩猟採集時代、3分あれば危険からのがれられるし、戦いも終了するから。
だから3分で警報は切れる。
長期間コルチゾールが出続けるということはPHA系が長期間発動し(警報が鳴り)っぱなしということ。
常に「闘争か逃走か」という緊張状態に脳みそ、身体がさらされている状態。
人間の進化の観点から本来3分間ほどしかコルチゾールは発動しないらしい。なぜなら、外敵から逃れるのに3分あれば十分。危機を脱出するのに3分あれば十分だったから。らしいです。
しかし現代ではスマホの「いいね」がつかないだとかだけでなく、様々なストレスを受け続けている。仕事締切だとか、住宅ローンだとか、コロナだとか。
つまりはPHA系発動しっぱなし。コルチゾール出っ放しなのである。長期間ストレスを受け続けている。
身体や脳に負担になっている。
現代生活そのものがストレスであり、そこへ来てのいきなりのスマホ社会ですから。
うつにまでならなくても・・・
実はスマホを触らなくても、脳みそはスマホのことに気を取られるようになる。
そしてスマホを触らないようにすることに気を取られるようになる。
つまり、脳みそをシングルタスク状態に持っていけなくなるのである。
そうなるとどうなるか。
常にマルチタスク状態。
長く集中力を持続できない。
覚えが悪くなるんだと。
これ実際の実験で結果が出ているらしい。
一日の中でスマホを使う時間が多い人は記憶力、集中力の面で、マホを殆ど使わない人よりも劣っていたんだと。
だから、スマホにはまらなくても、使いすぎることそのものにも脳に影響があるのだそうな。
あまり、スマホに脳みそを占拠されないようにしたいですね。
ストレスとは・・・

スマホによって他人の「リア充」を見せつけられて、みんながどれほど幸せかという情報を大量に浴びせかけられて、自分は損をしている、孤独な人間だと感じてしまうから、そんなことがストレスに。。。
スマホを使いすぎるほど孤独になり落ち込む。
それがストレス。
スマホを使いすぎるほど睡眠時間が減り、座っている時間が増える。
眠れなくなり、運動しないので気分が塞ぐ。
これもストレス。
長期間ストレスにさらされるとどうなるか→うつになる
身体に不調がおきる。
不眠、疲労感、発汗、お腹の調子が悪くなる、吐き気、食欲低下。
常に長期間ストレスにさらされることで、常に「闘争か逃走か」しか考えられなくなる。
即座に解決すべき問題以外は後回しにするようになる。
風呂に入らない、歯を磨かない、服を着ない、引きこもるだとか。
社会的に必要な緻密な行動がとれなくなる。
些細なことで強いいらだちがおこる。
頭が動かなくなる、周囲に気を配れなくなる。
モノ覚えが悪くなる。
それはつまり、「うつ」。
以上までが、「スマホ使い過ぎ」→「ハマる」→「長期間ストレスを受ける」→「体の不調」→「うつ」というメカニズムの話でした。
他にもいろいろある

ドーパミンシステムの影響を受けやすいのは中学、高校生、大学生など
ティーンエイジャーは前頭葉(意識部分)がまだ未発達。なので生きている実感や多幸感に酔いしれやすい。と同時に途方もない悲嘆にくれやすい。つまり報酬系で激しく興奮し、失望で激しくその反動を食らう。
スマホは大人よりも刺激が強すぎるということ。ハマりやすいし、うつにもなりやすいということ。
使用には注意がいるということ。
アルコールと同じだね。
ココんとこ、保護者の我々はよーく知っておいたほうがいいよ。
使い方によっちゃぁ、スマホは便利だけど諸刃の刃だよ。
幼児は?
そもそも使わせるなと言っていたよ。
ティーンエイジャーが危険なのだから、前頭葉どころか、まだまだ脳が未発達なのだからそりゃそうだよね。
いろんなものを実際に手で触って目で見て舐めて、嗅いで実際に感触を確かめなきゃダメだといっていたよ。
まさに。
大人は?
子供のいい手本になれといっていたよ。
寝る一時間前はスマホ、タブレットは使用を控える。
週3回ほど各45分ほど運動をしろ。
SNSは積極的に交流したい人と交流しろ。
よく眠って元気になりたければ・・・
アプリを使って一日どれだけスマホを使っているか現実を知れ!
腕時計、目覚まし時計を使え。
1日2時間スマホをOFFにしろ。
プッシュ通知をすべてOFFにしろ。
スマホの表示をモノクロにしろ。ドーパミンを抑えられるぞ。
運動中はサイレントモードにしろ。
チャット、メールの時間を決めろ。
人と会ってるときはマナーモードにしろ。カバンからスマホを出すな。
うーん、厳しいけど、できることからしようではないか。
響いたこと
スマホ使いすぎて精神的不調に陥らないためには、「睡眠、運動、他者との関わり」を大切にしなきゃならんということ。
そしてスマホはほどほどに使用するということ。おそらくこれが私にとって究極の最も大事な要素でしょう。
まとめ
というわけで本日はアンディシュハンセンさんの「スマホ脳」のレビューでした。
結局はスマホの使い過ぎは脳にも身体にも良くない。度を超えると依存し、「うつ」になるかもということ。
とはいえスマホは社会にはなくてはならないものだから、使い方をよく考えて、うまく付き合っていきたいですね。
普段僕が思っていること。
よく寝てよく食べて適当に運動して、気のおける人とバカ話で笑って盛り上がって、持ちつ持たれつで適当に過ごす。
まさにスマホはこの中の「適当に」ということなのかなと思いました。
ハンセンさんは結局のところ、「運動しろ」とそう言っているように感じました。
運動さえしていればなんとかなりそうな予感はします。
「スマホ脳」はなかなかいい本でした。
今回もごごちそうさまでした。











