
どうも、メケです。
本日はこの本の紹介です。
みなさん、勉強してなさそうな子供を見て、どう思いますか。
大丈夫かなとか思ったりしませんか。
気が付いたら子供以上に焦ったりして、子供にせかすようなことしていませんか。
受験を控えている子供の勉強について親はどんなことを心がけていけばいいのかなとか、そのヒントになればなと思ってこの本を手に取りました。
目次
こんな人におすすめ
勉強してなさそうな子供を見てやきもきする人。
受験を控えている子供を持つ親。
などなど。
どうやったら子供が自ら勉強に取り組んでくれるようになるか、そのヒントが欲しい人。
感想
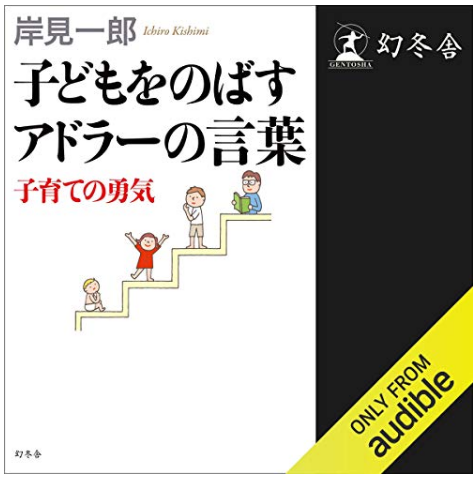
総括的に言えば、子育てのバイブル的な本だとは思いました。
しかし共感する部分もあればそうでない部分もありました。
子育てって人と人との関わり合いです。
分からない部分も多いし、思ったようにならないことも多い。
この本読みながら、そんな絵に描いた餅のようにいけば苦労しないんだけどねと思いつつ読む場面もありました(正直な感想)。
ヒントになる部分は有りますが、それに対する具体的なノウハウは詳しくは書かれていませんでした。
どちらかというと、子供と接するときの心構えかなー。
この本読む前の私どうだったか
例えば、宿題とかたくさんあるあるだろうに、全然しているように見えない時なんか。
「大丈夫かな」と思ったり、「やること終わってるのか」とか子供に聞いたりしていました。
もうね、学校から帰ってきてずっとスマホに取りつかれているとね、さすがに心配になってきちゃう。
子供以上に親の方が勝手にイライラしてたりなんかしてね。
この本読んでどう思ったか
そんな親の言動や態度が子供にどう映るのか、映っていたのかが客観的に分かるような一冊ですね。
子供はね、言われなくてもわかっていることを親に言われて、なんか先回りして上から目線で言われた気分になって余計に勉強する気をなくすらしいんです(この本によると)。
でもね、実際に私、子供に言われたことあります。
「お父さんのせいで勉強やる気なくなった」って言われたことあります。
子供にはきっと上から目線でわかってることを先回りして言われたような感じがしてたのでしょう。
この本の言葉を借りれば「子供の問題に親が土足で立ち入る行為」らしいです。
子供の問題であり、親の問題ではないとのことです。
そういうことに関しては親は土足で立ち入らなくてもいいそうです。
子供は「勉強は自分の問題だ」ってこと100も承知してるらしいです。
「いい成績を残せないと自分が困ること」も知っているんです。
もしも成績が振るわなくって思った学校に行けなかったとしても、その責任は自分で背負っていかないといけないことぐらい、子供はわかっているんです。
そのことを親はわかってあげましょう・・・と、アドラーはこの本で言っています。
子供のそういった思いを分かったうえで、「親として何か手伝えることはないかな」と思ってあげることの方がよっぽど子供のことを考えると建設的なんだそうです。
子供の問題=親の問題、ではないといわれています。
私としては、確かにそうではあるけども・・・・とは思ってしまいますが、この部分に関しては受け入れようと思いました。確かにどうなろうが「勉強するしない」は子供の問題です。
とはいえ、子供が路頭に迷えば親も困るだろうにとは思いますが・・・。だから他人事には思えないんですけど・・・とは思います。ここは、「勉強するしない」は子供の問題としてとらえろと言っています。
親もわかっているんです。子供の代わりに受験勉強してあげられないのも、志望校に合格できなかった人生を代わりに親が送ってあげられないのも。
つまり子供の身代わりになってあげられないことは分かっているんです。だから親は焦るんです。
この親の気持ちはこの本には書かれてなかったです。私の気持ちとして書きました。
しかしここで「なぜ勉強しないのか」叱るんではなくって「何か手伝えることはないか」という気持ちで接してあげてほしいというのです。同感です。
もうあと数年で子供は自立していくことを考えたら、子供の問題「勉強するしない」について、上から目線で「あーだこーだ」叱って、子供の問題に親が土足で踏み込んでいくようなことをしても、親子関係が悪くなるだけだと。
親子関係を悪くしては、子供が相談したいときに親に相談する気持ちにもなれません。
それは「子供の力になりたいと願っている親」にとっては「親子関係を悪くするのは本末転倒」なのです。同感です。
親子関係を悪くしている暇などないのだそうです。
勉強は本人がその気になれば黙っていてもやるようになるそうです。
どうやったら「その気」になるのか。
実は勉強の前に、勉強よりも大切なことがあったんです。
その大切な(個人的に本書の自分に響いた)ところをお話しします。
大切だなと思ったところをピックアップします
子どもが育っていく上で勉強よりも大事なことがある。
それは、
- 自分で決められるようになること
- 自分の価値を認められること
- 周囲に貢献すること
この3つが自立して生きていけるようにするには大事なんだそうです。
勉強は上記3つができると、勝手に自分で勉強していくようになるそうです。
ついつい、親は目の前のことにばっかり目が行ってしまいがちですが。
最終的には親がいなくても、自分でどうしたいか決められるようになることが大事

そのためには自分は生きているだけで「価値があるんだ」と思えること。
自分は大事な存在なんだと思えること。
そう思えると、自分のことは自分で決めて進んでいけるようになるとのことです。
だから、勉強も人の役に立てるのだからと自らやっていくようになるとのこと。
この辺り(なぜ自ら勉強するようになるのか)、ちょっと具体例が乏しくわかりにくかったです。
人の役に立てているんだと思えること
そのためには、親はほめるのではなく、手伝いなどしてくれた時は「ありがとう」とか「何々してくれて助かったよ」とかいうのがいいとのことです。
子供本人が人の役に立てることで自分の存在価値を認識し、役に立てることのうれしさを学べるそうです。
なので、勉強だけでなく家の手伝いも積極的に手伝ってもらいなさいとこの本では言っています。
受験生だからって家の中で特別扱いしなくていいですよと。
子供が手伝ってくれたら、決して「よくやった」とか褒めるなど(上から目線)はNGらしいです。
ありがとう、とか助かったよと感謝を伝えてくださいと。同感です。
手伝えることがあったら手伝うよという姿勢を親が見せること
そして周りは敵ではなく、困った時は周囲は協力してくれるんだと子供が思えること。
だから、子供自ら周囲に対して貢献し役に立とうと思えることが大事らしいです。
そういった気持ちをはぐくめるように親は子供に「手伝えることがあったら手伝うよ」という姿勢で、子供に接していくのがいいと・・・。
そのためには子供とはどうするのがいいか、具体例は書かれてなかったです。
子供と接するときの親としての心構えですね。
子供の問題に土足で踏み入るなということだと思います。
せかすな、上から目線はNGということなんでしょうね。
子供といい関係を築きなさい
もっと言えばケンカなんかしている場合じゃない。
子供の心のシャッターを下ろさせるようなことをしていてはいけないといったようなことが書かれていました。
具体的には叱ったり、ほめたりはしない方がいいだとか。
ほめるのも良くないらしいです(ほめられないとしない子になるかららしいのです)。
賛否両論あるでしょうけど、一理あるなとは思いました。
思春期付近の子供には言えますね。
下手な褒め方すると逆に受け止められてしまいますから。
そんな意味で言ったんじゃないよとあとで弁明が必要になりますから。
よく、怒るのと叱るは違うといいますが、この本では上から目線で子供の問題に土足で立ち入る点ではどちらも同じだと言っています。
子供の問題は子供の問題。
例えば勉強しなかったことで、望んだ学校に進学できなくてもそのことは子供自身が背負っていく問題。
親の問題ではないのだと・・・。この辺いろいろ意見はあるとは思いますが、一理あるとは思います。
子供の悩みを聴いて、解決できるように手助けする方が大切とのことです。ここは納得です。
これからどうするか

子供は「勉強するしないは、自分の問題と分っているんだ」と私自身に言い聞かせます。
上から目線はNG。
岸で見守ります。
危なければ助けに行きます。
子供の問題をサポートするつもりで接します。
まだ若いんだから、失敗するなら早い方がいいし。
失敗してもそこから学べることもあるだろうし。
「相談しやすい親」でい続けたいなと思います。
「ありがとう」「助かったよ」はもっと子供に伝えていきます。
まとめ
本日は「子供が自ら勉強するにはどうしたらいいかな」というのがあって、この本を手に取りました。
結論は「勉強するしない」は子供の問題。気にせんとこう、ほっとこうと思いました。
そのかわり、「ありがとう」「助かったよ」は意識して、上から目線は気を付けて、子供が必要な時に相談しやすい環境を作っていけたらいいなって思いましたね。
まぁ、でもね、正直「子供の性格、特性」も見つつじゃないと、「一律にはちょっとね」なんて感じるのは私だけでしょうか。
子供がどうであれ、「あまり、子供の問題に土足で踏み込み過ぎないこと」ここは大事そうですね。
ということで本日は「子供を伸ばすアドラーの言葉」の本についてのレビューでした。
もっと「ありがとう、助かったよ、何か手伝えることなーぃ?」というのを増やした方がよさそうですね。
今日も最後まで読んでくださいましてありがとうございました。













