
どうも、メケです。
なかなか、小説までいきません。
今回も一冊読み切り本です。
読み切りとはいえ、この本15回ほどAudibleで聞きました。
通勤時間を利用してAudible聞いてるんですけど、たまたまこの本が目に入って、1冊読み切りだったので手に取りました(小説は一冊が長いうえに続編で何冊もあるので気持ち的に気合がいる。読みだすと止まらないのではまり込む覚悟がいるので)。
左がKindleの表紙、右がAudibleです。
どちらも同じ本です。
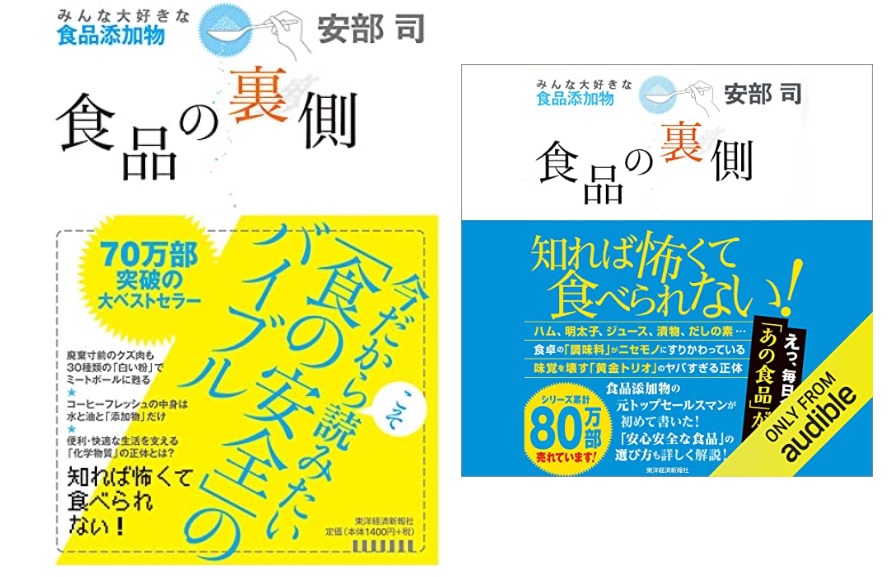
挿絵の左上見てください。KindleもAudibleともに「みんな大好き食品添加物」だって。「んな訳ねぇだろ」ってつい手にとっちゃいますよね。うまいキャッチコピーです。やられました。
目次
この本読む前の食品添加物のイメージ
食品添加物にいいイメージはないですね。体によくない。できれば摂りたくない。
でもまったく摂らないわけにはいかない。
仕方ない。許容はしている。といった感じでしょうか。
食品添加物の現状がどれほどひどいかとか、どれだけ食品添加物の恩恵を受けているだとか、そんなことまでは考えてなかったですね。
食品買う時に包装紙の裏側を見ていたかどうか。見てはいた。けど、ホント見てただけ。たくさん表示されているモノは買わないようにしていた。
そんなレベルでした。
実際読んでの感想

正直驚き。
食品添加物の表示ルールの例外として「表示免除制度」があるということを知らなかった。まとめて一括表示できるということ。何種類使われているのか包装紙の裏側見ただけではわからないということ。まさに驚き。
食品包装紙の裏側に表示されていないモノもたくさんあるということを知らなかった。
一括表示
例えば「ph調整剤」「香料」「保存料」。
これらは何種類も食品添加物が使われているけど、一括に表示されている。同じ目的ならば一括で表示していいっていうルールがあったのだ。1種類しか使われてないわけじゃないことを知っとかないといけない。
このほかに、マーガリンの「乳化剤」「酸化防止剤」とかも同じ。
これら表示の裏側に何種類もの食品添加物が使われていることを忘れちゃぁいけない。
キャリーオーバー(表示免除)
食品添加物が入っているのに無表示でいいというルール。
例えば「焼き肉のたれ」。
焼肉のたれには原材料で「醤油」「みりん」などメインで使われているが、これら「醤油」「みりん」にもまた「食品添加物」は使用されている。がしかし、「焼き肉のたれ」の原材料表示には「醤油」「みりん」の表示のみだ。仕入れ先で使っている食品添加物まで表示されていない。だからそれ以上のことは分からない。でも、それでいいことになっている。
1本300円ほどで買える「焼き肉のたれ」に本物の醤油やみりんが使われているわけがない。安いということはそれだけコストを抑える何かをしているということ。
この本の著者はそのことに「気付けよ」「疑問に思えよ」と、そう促している。まるで「都市伝説の関暁夫」状態だ。「お前ら、知らねぇぞ」と・・・・。素直に安いのはなんでかな?って感じてください。その答えは包装の裏側にかいてありますと・・・。
そういうこと知っとかないと気づけないよね。省略表示殆どの商品でされているから。特に加工食品。
何から何まで全て食品添加物を書いていたら書ききれないから、どこかで切らないと仕方ない。だから、そういう表示免除制度があるみたいだ。ここんとこ知っとこう。
加工助剤(使ったけど残ってないものは表示しなくていい)
加工工程で中和処理などして出荷時に残ってないものは表示しなくていい。
たとえばみかんの缶詰。
みかんの皮は苛性ソーダと塩酸で溶かして除去しているけど塩酸は苛性ソーダ中和されるので表示してません・・・とか。
たとえばカット野菜とか。
次亜塩素酸ソーダという殺菌剤。これも pH 調整剤で 加工の途中で中和されてなくなるので表示してないだとか。
パッケージが小さすぎて表示できないモノ
読んで字のごとく。30cm2以下の包装紙には書かなくていいようになっている。
例えば、納豆にパックに入ってる醤油ダレ、カラシ。スーパーで刺身コーナーに置いてあって、無料でもらえる刺し身醤油、わさびとか。なんで無料なのか考えたことあります? 食品添加物を駆使してコストを最大限抑えてそれ風な調味料を作っているからです。ちゃんとしたものでちゃんとしたものを作ればそれなりのお値段します。
例えば本物のわさび、あれ1本で4~500円します。丸大豆を1年間熟成発酵させた醤油は1本1000円近くします。本物は熟練した技術とこだわりの手間暇によってそれなりのお値段になるんです。安いにはそれなりの理由があります。
店内で加工処理したモノ(総菜)
みなさん周知のこと。最近では店内で調理したものにも表示している店多いですよね。ありがたい。以前はそんなことなかったし、よく見てみれば表示していない調理済み品もまだまだ多い。
この著者はどういった人か

食品添加物の元営業マン。ある時、自分も自分の家族も一消費者であることに気づく。自分や家族に食べさせたくないものに関わる仕事はできないと退職した人。ある意味目覚めた人。
生産加工現場で食品添加物をどう扱ってきたのかを知っている生き証人。食品添加物に関してはこの人の右に出る人がいないほどの知識と経験を持っている人らしいです。
食品添加物 影もあれば光もある
この人いわく、食品添加物によって工場は生産性が上がりコストを抑えられ恩恵を受けてきた。同時に消費者は時間や便利さという恩恵を受けてきた。食品添加物をすべて悪者にしてほしくはないと。恩恵という光の部分もあるが同時に影の部分もある。影とは健康や食の崩壊とか。このへんは個人自身がかぶるところである。だからこそ、必要なことは知った上でうまく食品添加物と付き合ってほしいと、この著者は本書で言っている。
確かにそうだよねとは思いました。
いつでもどこでも気軽に手間を掛けずに食べ物にありつける。食品添加物のおかげ。だけども、やっぱりそれらを食べるからには不必要に食品添加物を取りすぎないように気をつけたいところですね。
なぜ食品添加物に興味がでてきたか
最近始めた「マクロ管理法」がきっかけです。
マクロ管理法とは三大栄養素(たんぱく質、炭水化物、脂質)とトータルの摂取カロリーをコントロールする手法。この手法を使って自分の望む肉体を手に入れようということです。で、私毎日マクロ管理法を実践しています。今4週間目になる。かなり習慣になってきている。うれしい話。
で、その栄養素の表示を見るのに食品の包装紙裏側をよく見るのです。同時に食品添加物表示もよく見てしまう。 それが食品添加物が気になり始めたきっかけです。
あともう一つ。プロテインについても。プロテインも毎日、しかも長期に飲み続けるモノ。最近では飲みやすく味のクオリティも高い。なぜか。食品添加物のおかげなんでしょうね。合成甘味料・・・、気になるところです。私プレーンのプロテインをメインで飲んでます。
どうしたいか
店の特売で異様に安い加工食品は手を出さないほうが良さそうですね。
タレや漬物ぐらいは自分でつくろうかな。
加工モノは食品添加物かなり多いぞ。
できるだけ形あるものを購入したい。
最近またプロテイン飲み始めたんだけど、やっぱり食品添加物気にはなる。毎日、日に何回か飲むものだからプレーンのほうが安心だよね。だからって飲みづらいのを我慢してプレーンなプロテインばかりっていうのも嫌だしね。そんなわけで僕はプレーンのプロテインにバナナ味とかココア味を希釈して飲んでる。味付きのプロテインは僕には甘すぎるから、プレーンで希釈するぐらいがちょうどいい。度を越さなければいいんじゃないかなとは思っている。発がん性のある食品添加物は使われてないか確認しといたほうが良さそうですけどね。
まとめ

この本は久々にごちそうでした。
最近いい本によく出会える。
感謝。
ついでに食品添加物危険度ランキングの記事見つけましたのでリンク貼っときます。
代表的な10個ぐらいの危険な食品添加物の名前知っときたいですね。
ただ、この著者は無理して覚えなくてもいいですと言ってました。台所においてある調味料名で馴染みのない名前がずらりと並んでるものは注意したほうが良いですとのことです。までもね、包装紙の裏側いつも見ていたら下記のうち半分以上ぐらいの食品添加物はよく見かけます。これらを毎日毎日多量に食べるのは避けたいですね。
- 亜硝酸ナトリウム
- アスパルテーム
- アセスルファムK
- 合成着色料
- 安息香酸ナトリウム
- ソルビン酸カリウム
- OPP,TBZ
- 臭素酸カリウム
- カラギーナン
- BHA
というわけで、この本読んで「食品添加物の恩恵をある程度は受けつつも賢い消費者になりたいですね」と思った次第であります。
今日も最後まで読んで下さいましてありがとうございます。
そんじゃぁ、またね。













